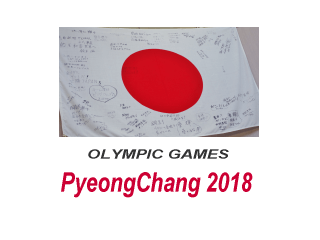ノルウェー 初の五輪団体金メダル 日本は6位
2018年2月19日(月) 平昌(KOR)HS142/K125
Men’s Team
| 金 | ノルウェー | 1098.5pt | 545.9pt 1位 | 552.6pt 1位 |
| ダニエル-アンドレ・タンデ | 141.8pt 1位 | 145.5pt 1位 | ||
| アンドレアス・ストエルネン | 134.6pt 1位 | 139.8pt 1位 | ||
| ヨハン-アンドレ・フォルファン | 132.3pt 3位 | 129.7pt 3位 | ||
| ロベルト・ヨハンソン | 137.2pt 3位 | 137.6pt 3位 | ||
| 銀 | ドイツ | 1075.7pt | 543.9pt 2位 | 531.8pt 2位 |
| カール・ガイガー | 139.4pt 2位 | 131.7pt 2位 | ||
| シュテファン・ライエ | 124.1pt 3位 | 126.0pt 3位 | ||
| リヒャルト・フライターク | 134.5pt 2位 | 135.8pt 1位 | ||
| アンドレアス・ヴェリンガー | 145.9pt 1位 | 138.3pt 2位 | ||
| 銅 | ポーランド | 1072.4pt | 540.9pt 3位 | 531.5pt 3位 |
| マチェイ・コット | 128.3pt 4位 | 127.0pt 3位 | ||
| ステファン・フラ | 129.8pt 2位 | 134.8pt 2位 | ||
| ダヴィド・クバツキ | 139.7pt 1位 | 135.3pt 2位 | ||
| カミル・ストッフ | 143.1pt 2位 | 134.4pt 4位 | ||
| 4 | オーストリア | 978.4pt | 493.7pt 4位 | 484.7pt 4位 |
| 5 | スロベニア | 967.8pt | 492.4pt 5位 | 475.4pt 5位 |
| 6 | 日本 | 940.5pt | 475.5pt 6位 | 465.0pt 6位 |
| 竹内 択 | 113.6pt 6位 | 110.5pt 6位 | ||
| 伊東 大貴 | 117.6pt 4位 | 109.8pt 6位 | ||
| 葛西 紀明 | 112.2pt 6位 | 117.9pt 4位 | ||
| 小林 陵侑 | 132.1pt 6位 | 126.8pt 6位 | ||
| 7 | OAR | 809.8pt | 409.6pt 7位 | 400.2pt 7位 |
| 8 | フィンランド | 790.4pt | 397.5pt 8位 | 392.9pt 8位 |
ジャンプ競技の締めくくりとなる団体戦は、胸躍るスリリングな好ゲームとなった。
メダル候補と目されていたノルウェー、ドイツ、ポーランドがイコールコンディションの中で存分に力を発揮し、1本目が終わった時点でわずか0.5ptの中にひしめきあった。
圧倒的な優勝候補はノルウェーだった。
昨季WC団体6試合の最後の2試合(ヴィケルスン、プラニツァ)を連勝し、今季もヴィスワ、ルカ、ティティゼーーノイシュタットとシーズンを跨いで5連勝。とどめにフライング選手権をも制し団体6連勝と手の付けられない強さを誇っていた。
直近のザコパネこそ3位に終わったが、この時はタンデが体調不良で欠場し、代わりに初メンバー入りとなったリンビークを起用するなど、ベストメンバーとは言い難かった。
今のノルウェーには穴がない。4人の選手が―いや、ファンネメルも含めて5人の選手が―いずれもアンカーを務められるだけの力を持っている。
事実、6連勝中もストエルネン、ヨハンソン、フォルファン、タンデとアンカーが入れ替わった。
このチームのエースはタンデだと思われるが、6連勝の中でタンデをアンカーに使ったのは1戦のみ。このあたりのシュトックルの采配は興味深い。
この試合では、NHとLHの銅メダリストであるヨハンソンをアンカーに起用。彼ももちろん素晴らしかったけれど、試合を決定づけたのはタンデだった。
5.0pt差での折り返しで本当に先が読めない2本目で、1番手のタンデの一発が流れを大きく変えた。これにより後続の3人は余裕を持って戦えたんじゃないかと思う。
ノルウェーは、1988カルガリー大会から採用された五輪団体戦で初の金メダル。
今大会はこれで、個人で銀1つ、銅2つ、そして団体で金。
最高のオリンピックだったんじゃないかな。特に出場3種目全てでメダルを獲得したヨハンソンにとってはね。
先述のノルウェーの6連勝を止めたのが、もう一つの優勝候補と見られたポーランド。
上り調子のフラ、クバツキらが健闘したものの、アンカーレベルの4人を揃えたノルウェーには敵わなかった。
もっともポーランドは、2016クリンゲンタールのWCでようやく初優勝を遂げた団体後進国。これが五輪での団体初メダルとなったが、試合巧者ぶりはノルウェーに一日の長があったか。
そのポーランドと最後まで熾烈な銀メダル争いを演じたドイツ。
最後は、NHとLHの金メダリストの直接対決で雌雄を決したが、ストッフがまたも大きく踏み外してしまったのに対しヴェリンガーはそつなくまとめて銀メダルを射止めた。
ヴェリンガーは、これで金1つと銀2つ。彼にとっても最高のオリンピックとなった。
一方、日本のメダルの可能性は端から極めて小さなものだった。
トップ3との力の差は大きく、欲張ったとしても現実的な目標は4位だった。
その位置をオーストリアとスロベニアとで争うことが予想されたが、この両者を退けて4位になれば、日本にとっては大成功と言えただろう。
実際に、日本はこの2ヵ国一と緒にセカンドグループを形成し、トップ3とは別の次元で戦うこととなったが、結果はグループの中で一番下の6位。
イコールコンディションでは波乱も起きようがない。残念ながらこれが今の力。
日本にとっては厳しいオリンピックだった。
小林陵侑のノーマルヒル7位入賞が最高位。
1992アルベールビル大会から7大会続いていたラージヒルの入賞も途絶えてしまったし、団体も2006トリノ6位と並ぶワースト2位。(ワーストは初開催となった1988カルガリーでの11位)
この結果を受け、斉藤智治監督が、今後の立て直し策としてCOCフル参戦に言及したようだけど、そんなことはジャンプファンであれば今までさんざん言ってきたことであり、このブログでも何度も言及して来たし、最近も触れたばかり。
金がなくて派遣できないものだと思ってきたし、金は沸いて出てくるものではないので、無い袖は振れないということに対しては理解もしてきた。
でも、なんだかそれが理由でもなく、やらなきゃいけないとはわかっていたけれど、やってこなかっただけのことのようにも受け取れる。
これも先日書いたが、日本は、コーチその他のサポートスタッフの力、それを動かし支える連盟などの組織力、さらにはマテリアルの開発能力などのすべての面で、ノルウェー、ドイツ、ポーランド等の強豪国に相当な遅れを取っていると思う。
厳しい結果に終わったこの五輪を猛省すべきは、選手たちではない。